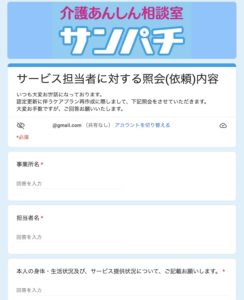R5.3.1(水)サンパチ日報管理者K編@生産性向上
AM
Zoom朝礼
↓
関係機関電話対応
↓
求職者見学者対応
PM
介護現場における生産性向上推進フォーラム(オンライン)
↓
帰宅
【今日のいいこと】
本日、午前中は、公開中の求人を見て、見学の方がいらっしゃいました。
元々、10年前くらい?に、私と面識のあった方ではありましたが、あまたあるケアマネ求人の中で、サンパチに興味を持っていただいた理由が気になり聞いてみました。
・勤務時間など柔軟に対応します。(求人票)
・職場見学大歓迎です。(求人票)
(感染対策にて見学不可の事業所もあった)
・日報(ブログ)が楽しそうだった。
などの理由からとのことでした。
面接ではないので、ざっくばらんに、色々とお話でき、トイレの電気と台所のゴミ箱まで、隅々まで見学していただきました😌
午後は、厚生労働省の介護現場における生産性向上推進フォーラムにオンラインで参加しました。
https://kaigo-seisansei.com/

・介護現場における生産性向上のOUTPUTは、ケアの質の向上、介護の価値を高めること、である。
・国が主導して、介護現場の生産性向上に取り組んでいるが、普及していない現状がある。
当社でも生産性の向上、業務効率化には力を入れて取り組んでいるところであります。
https://ecomo38.com/productivity-list
最近では、クラウド勤怠システムを導入し、出退勤の打刻、有給休暇や勤務変更申請など、パソコンやiPhone、iPadで手軽に行えるようにしました。
周囲の目を気にしながら、ハンコをついてもらうために紙の申請書を回す必要なく、ネット上で主任と管理者が承認します。
そして、そのまま、給与計算にデータ移行できるので、私も楽になりました。
ケアマネジメント以外の時間を減らすことで、利用者のケアマネジメントにかける時間が増えると考えます。
会社の生産性は、仕事量やICTツールだけで決まる訳ではないことは、重々承知しています。
最終的には、人です。
自分も含めた人づくり、組織づくりです。
組織としてまだまだ足りない部分もあります。
小規模事業所だからこそのメリットを生かし、今後もフットワーク軽く、業務効率化、生産性向上、ケアマネジメントの向上に取り組みます。
今日も一日おつかれさまでした。