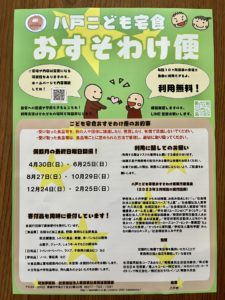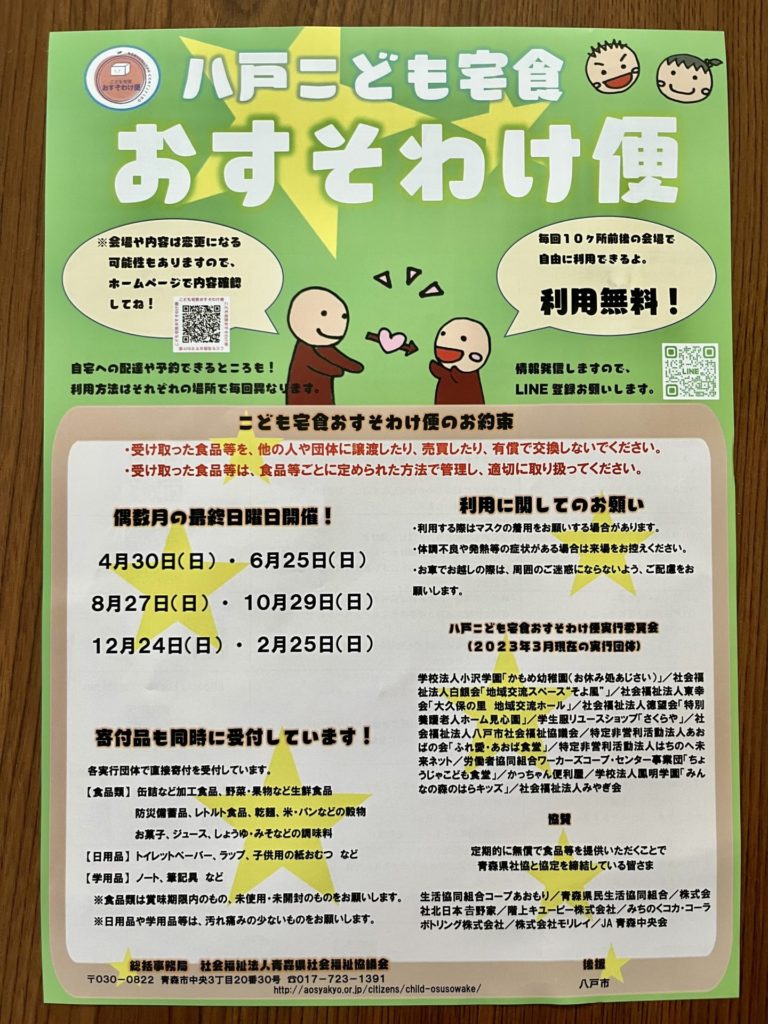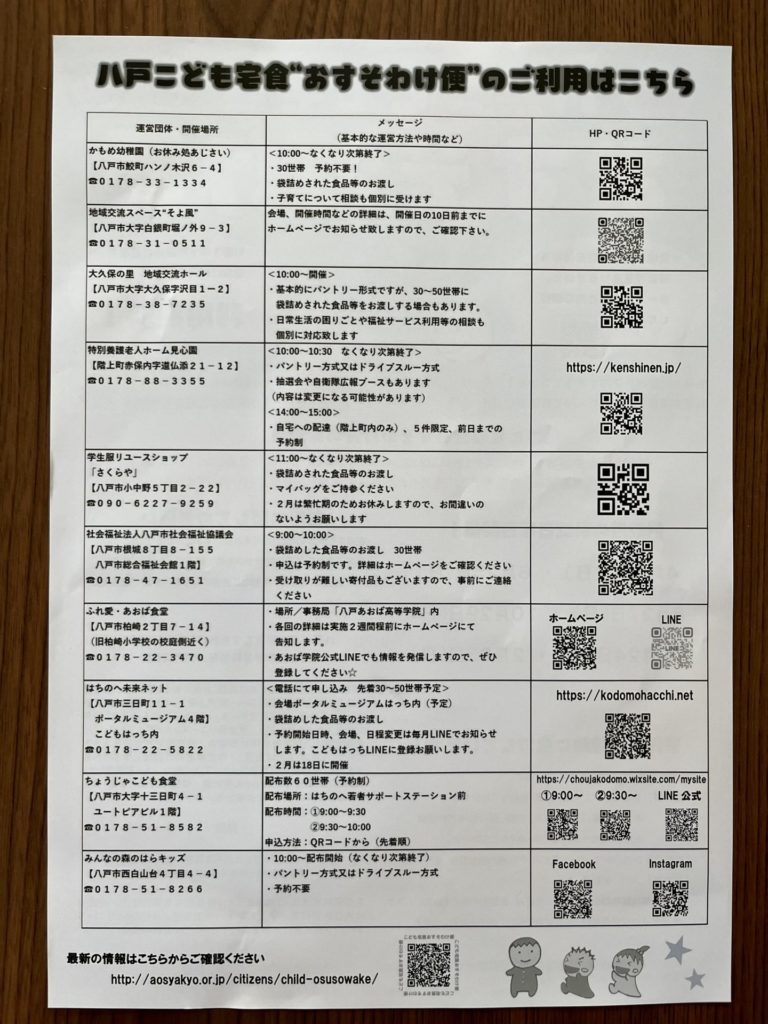R6.2.14(水)サンパチ日報管理者K編@研修&懇親会
AM
朝礼
↓
サービス担当者連絡調整
↓
社員面談
PM
サービス担当者会議日程調整
↓
管理業務
↓
スクールソーシャルワーカー高校訪問・面談
↓
帰宅
【今日のいいこと】
本日はとても暖かく過ごしやすい一日でした。
風だけが強く、サンパチの旗のポールが折れてしまわないかだけに集中しました。
そして、世間はバレンタインデーだったのですね。
そんなことを忘れるほどに、大変充実した生活を送っております。
さて先日、2月3日節分の日👹に、青森県社会福祉士会三八支部の研修会と懇親会が開催されました。
研修は、八戸市立市民病院の工藤貴徳医師をお招きし、医師とソーシャルワーカーが連携・協働した事例を通して、医療ソーシャルワーカーの役割と専門性について学びを深めました。


以下、支部長の挨拶でも述べた内容ですが、
三八支部では年3回程度研修会を開催しています。
普段は、社会福祉士の会員中心に20〜30名程度の参加となっていましたが、今回は50名を超える申し込みをいただきました。
また、社会福祉士、ソーシャルワーカーはじめ、ケアマネジャー、看護師、薬剤師、地域包括支援センター、障害者の相談支援専門員、市役所、市議会議員の方など、いつも以上に多様な職種、業種の皆様にご参加いたたきました。
私の知る限り、三八地域において、「医師とソーシャルワーカーの連携、協働」について、医師自らが講師としてお話くださるという研修は初めて、三八地域史上初ではないかと思います。
一般論として、私たちソーシャルワーカーは、相談援助、社会資源につなげる、といった役割の中で、その実践に対する結果が見えにくい、評価を数値化することが難しく、効果測定がしにくいという課題を抱えています。
医療専門職ではない私たちは主に生活課題の改善に取り組みますが、生活の質は簡単には数値化できません。
よってエビデンスを確立しにくいといった課題も抱えています。
今回、医師がソーシャルワーカーの役割、専門性に関心を持ち、自ら調べ、言及すること自体、今まであり得なかったことで非常に貴重な機会となりました。
外来診療ではどうしようもできないケースをMSWに相談することで病態の改善につながること、医師がソーシャルワーカーを医療チームの一員として対等な立場で信頼していること、そして、その役割を理解し評価していること、そのことを初めて医師の口から直接伺うことができ、とても光栄で、ソーシャルワーカーたちの自信につながる内容だったと思います。
特に、医師が医療ソーシャルワーカーへ相談したことをきっかけに、糖尿病数値のHbA1cが如実に下降しているグラフの提示は大変興味深く、ソーシャルワーカーの実践の価値を数値化するひとつの指標の形になり得ると新たな気づきを得ました。
そして、何より、福祉職に対してあんなにもお酒の付き合いがいい医師がいることに大きな衝撃を受けました。

18:00開始の懇親会、2次会終了まで深夜1時までお付き合いいただきました。
ソーシャルワーカー(ケアマネ)の実情と愚痴まで聞いていただきました。
八戸市立市民病院、内分泌・糖尿病内科 部長 工藤貴徳先生の、穏やかな語り口調、優しく親身に話を聞いてくださる人柄が素晴らし過ぎました。
工藤先生、ありがとうございました。
ソーシャルワーカーとしての誇りを旨に、これからもケアチームとして連携させていただきたいと思います。
今日も一日おつかれさまでした。